硫黄島で米軍の猛攻を許した日本軍の誤算
沖縄戦と本土決戦の真実②
アメリカ軍の猛攻に制圧される地下陣地
上陸2日目の2月20日、アメリカ軍は元山(げんざん)地区と擂鉢山(すりばちやま)へ向けて前進した。日本軍守備隊は徹底抗戦したが、夕方には、南海岸の内陸部にある千鳥飛行場が占領された。
アメリカ軍は攻撃目標を摺鉢山に定め、陣地をしらみつぶしに制圧する作戦をとった。地下坑道は火炎放射器で焼かれたり、ガソリンが流し込まれて燃やされたり、ブルドーザーで出入口を塞がれたりした。
23日午前10時15分、摺鉢山の頂上に星条旗が翻った。正午過ぎ、改めて別の星条旗が掲げられた。有名なピューリッツァー賞受賞の写真は、このとき撮影されたものである。
勢いを得たアメリカ軍は島の中央部にある元山飛行場地区に猛撃を加えてきた。守備隊は岩山に築いたトーチカ群や地下陣地からの重火器で敵の進軍を食いとめた。
栗林はアメリカ軍の上陸前、将兵の士気を鼓舞するため、6項目から成る自筆の「敢闘ノ誓」を全軍に配布し、不屈の闘争心を求めた。そのうちの3つを引用しておこう。
一 我等ハ爆薬ヲ擁(イダ)キテ敵ノ戦車ニブツカリ之ヲ粉砕セン
一 我等ハ各自敵十人を殪タオサザレバ死ストモ死セズ
一 我等ハ最後のノ一人トナルモ「ゲリラ」ニ依ッテ敵ヲ悩マサン
まさに決死の覚悟である。ゲリラ戦を掲げたのは、栗林が戦略戦術に精通し、硫黄島の地形の特徴を把握していたからにほかならない。
栗林中将自らが率いる日本軍最後の突撃──
上陸部隊は6万人にも膨れあがったが、アメリカ軍の予想を大きく上回る日本軍守備隊の攻撃力によって上陸部隊は死傷者が増加。双方の部隊は消耗戦の様相を呈した。だが、多勢に無勢とあって、26日に元山飛行場が占領され、周囲の主要な要塞も次々に制圧された。
3月8日、玉名山(たまなやま)で奮戦してきた混成第2旅団を率いる千田貞季(せんださだすえ)少将は、武器弾薬が尽きたことから、残存兵力を率いて総攻撃を敢行した。千田以下約700人が戦死し、生き残った将兵は洞窟陣地に立てこもってゲリラ戦をくりひろげた。
西竹一(にしたけいち)率いる戦車第26連隊は地中に埋めた戦車の砲撃に加え、敵の不意を突いて戦車を出撃させてアメリカ軍に多大な被害を与えたが、敵戦車との砲撃戦、バズーカ攻撃などで壊滅した。西は19日から20日にかけて戦死したとみられる。
アメリカ軍は兵団司令部がある島の北東端に迫り、司令部周辺は熾烈な砲撃や空爆にさらされた。
栗林は3月16日夕刻、大本営へ決別電報を発した。電文の最後に3首の和歌を添えた。その一首に「国の為重きつとめを果し得で/矢弾尽き果て散るぞ悲しき」がある。
翌17日、同日付で陸軍大将に親任された栗林は、各部隊に同日夜に総攻撃を決行すると伝え、「余ハ常ニ諸子ノ先頭ニ在リ」と、信条にしていた率先垂範を示した。その後、総攻撃の時機を見直し、市丸利之助(いちまるりのすけ)率いる海軍残存部隊と合流した。
26日未明、栗林は約400人の陸海軍混成部隊を率いて地下壕を出ると、アメリカ軍の野営地を襲撃した。やみくもに突進するバンザイ攻撃ではなく、敵情を見極めての急襲だった。アメリカ軍は混乱に陥り、死傷者が続出した。
だが、敵の援軍によって混成部隊は全滅。栗林や市丸の最期については諸説ある。2人の遺体は確認されていない。
日本軍の戦死者は、防衛省防衛研究所によれば約1万9900人(厚生労働省は約2万1900人)、捕虜は1033人。アメリカ軍は戦死者6821人、戦傷者2万1865人。死傷者数2万8686人は、日本守備隊を上回る。
硫黄島は明治24年(1891)以来、日本固有の領土である。守備隊は極限状況のなか、祖国の防衛を願いながら、自国の領土で1カ月以上も持ちこたえた。
監修・文/松田十刻
- 1
- 2



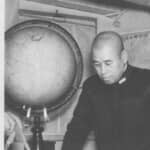
20200007-11-西京丸の奮戦(黄海海戦にて)-150x150.jpg)

